基本用語
消防設備士試験の勉強を始めて、最初に面倒だと思うのが、基本用語の暗記。特に「防火対象物」と「消防対象物」は試験でも頻繁に聞かれているが、違いがわかりにくいですね。これらはいずれも消防法第2条に書かれているので、とりあえず法律を見てみましょう。
下記の色を付けたところにそれぞれの言葉の意味が書かれています
第二条 この法律の用語は左の例による。
2 防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。
3 消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう。
4 関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。
5 関係のある場所とは、防火対象物又は消防対象物のある場所をいう。
6 舟車とは、船舶安全法第二条第一項の規定を適用しない船舶、端舟、はしけ、被曳船その他の舟及び車両をいう。
7 危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
8 消防隊とは、消防器具を装備した消防吏員若しくは消防団員の一隊又は消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第三十条第三項の規定による都道府県の航空消防隊をいう。
9 救急業務とは、災害により生じた事故若しくは屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故(以下この項において「災害による事故等」という。)又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち、医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によつて、医療機関(厚生労働省令で定める医療機関をいう。第七章の二において同じ。)その他の場所に搬送すること(傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応急の手当を行うことを含む。)をいう。
消防法
このように「防火対象物」は「消防対象物」はかなり近い表現になっていますね。何が違うの???もう一度抜き出してみると、最後の表現がちょっと違うだけ!!
まとめると
- 防火対象物とは、~若しくはこれらに属する物をいう。
- 消防対象物とは、~又は物件をいう。
のようになっています。この違いを覚えればOK!これは試験では毎回のように出てくる重要ポイントなので、覚えておきましょう。
ということで、覚え方は、下の「消防対象物」だけを覚えて、「防火対象物」は、そうではない方と考えればよいでしょう。
消防対象物には、「物件」が入るから、覚え方は
「しょぼい物件」
これでOK!!語呂合わせがしょぼい(!?)という話もあるが、これで十分、答えられるので覚えていただければと!!
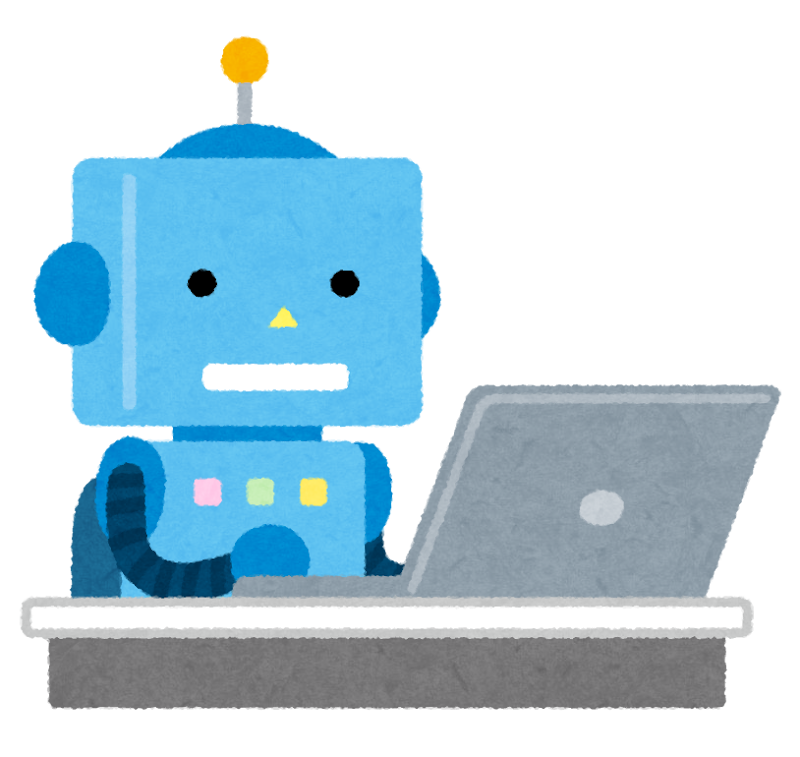
消防対象物 ⇒ 物件
「しょぼい物件」
頻繁に問題に出るので、必ず覚えてね
防火対象物(消防法施行令別表第1)
消防用設備の設置義務のある建物、「防火対象物」は、消防法の令別表第一というもので分類されています。以下は抜粋ですが、20種類に分類され、更に、イ、ロ、ハ、二や、”16の2”、”16の3”のように細かく分類されています。消防設備士の試験でこれらを覚えて行いと合格できない、ということはありませんが、概要を覚えておくと、教科書を読んで勉強するときや、問題の解説を見るときに、いちいち表に戻らなくて済むので、勉強の効率が上がります。
なお、過去問(問題集)を見ると、覚えていないと解けない問題もあるようですが、実際に出題される可能性は低そうです。いまのところ…
しかし、項目が20もあるので、覚えるのが大変です。
| 1 | イ | 劇場・映画館・演芸場・観覧場 |
| ロ | 公会堂、集会場等 | |
| 2 | イ | キャバレー・カフェー・ナイトクラブ |
| ロ | 遊技場・ダンスホール | |
| ハ | 性風俗店 | |
| ニ | カラオケボックス | |
| 3 | イ | 待合・料理店 |
| ロ | 飲食店 | |
| 4 | 百貨店・店舗型マーケット・展示場 | |
| 5 | イ | 旅館・ホテル・宿泊所 |
| ロ | 寄宿舎・下宿・共同住宅 | |
| 6 | イ | 病院・診療所・助産所 |
| ロ | 特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・身体障害者更生援護施設 | |
| ハ | 老人デイサービスセンター・軽費老人ホーム・老人福祉センター・保育所(保育園)・児童養護施設・地域活動支援センター・小規模多機能型居宅介護施設・短期入所施設・自立支援施設・通所施設等そのほかの社会福祉施設 | |
| ニ | 幼稚園・特別支援学校 | |
| 7 | 小学校・中学校・高校・大学・専門学校・その他各種学校 | |
| 8 | 図書館・美術館・博物館・その他これらに類する施設 | |
| 9 | イ | 蒸気浴場・熱気浴場 |
| ロ | 公衆浴場 | |
| 10 | 車両の停車場、船舶または航空機の発着場 | |
| 11 | 神社・寺院・教会 | |
| 12 | イ | 工場・作業場 |
| ロ | 映画スタジオ・テレビスタジオ | |
| 13 | イ | 自動車車庫・駐車場 |
| ロ | 飛行機、回転翼機の格納庫 | |
| 14 | 倉庫 | |
| 15 | 事業場 | |
| 16 | イ | (1)項から(15)項までのうちの特防に該当している複合用途防火対象物 |
| ロ | その他の複合用途防火対象物 | |
| 16の2 | 地下街 | |
| 16の3 | 準地下街 | |
| 17 | 重要文化財・重要有形民俗文化財・史跡 | |
| 18 | アーケード | |
| 19 | 山林 | |
| 20 | 舟車 |
そこで、覚え方がこちら。各項の代表的なものを抜き出して、語呂合わせを作りました。ちょっと(かなり?)無理のある語呂合わせもありますが、そこは勢いで。覚えていないと受からないということはないけど、覚えておくと便利
| 項 | 代表 | 覚え方 |
|---|---|---|
| 1 | 映画館 | No.1映画 ※「全米No.1」とか「興行収益No.1」とかよく見るよね |
| 2 | ダンスホール | 二人でダンス |
| 3 | 料理店 | 酸辣湯(サンラータン)を注文 ※ここは、参鶏湯(サムゲタン)でもよいかと… |
| 4 | マーケット | 夜店(よみせ)でお買い物 |
| 5 | ホテル | ホテルへゴー ※合意(ごうい)のうえでホテルへ、もあり |
| 6 | 病院 | 肋骨(ろっこつ)追って病院へ |
| 7 | 学校 | 7歳になったら小学生 |
| 8 | 博物館 | ハチ物館 |
| 9 | 公衆浴場 | 九州温泉 |
| 10 | 停車場 | テン車場 |
| 11 | 神社 | 手を合わせてパンパン ※1回1回丁寧に柏手を打つイメージで |
| 12 | 工場 | 12ヶ月間忙しい工場 |
| 13 | 駐車場 | 秘密(ひみつ)の駐車場 ※穴場の駐車場、みんなに教えたくないね |
| 14 | 倉庫 | 重要(じゅうよう)なものは倉庫へ |
| 15 | 事業所 | じゅうごうしょ ※ジギョウショ、ジュゴウショ、ジュウゴウショ… |
| 16 | 複合用途防火対象物 | いろいろある施設 |
| 17 | 文化財 | いなかの文化財 |
イメージと勢いで覚えられそうかな?
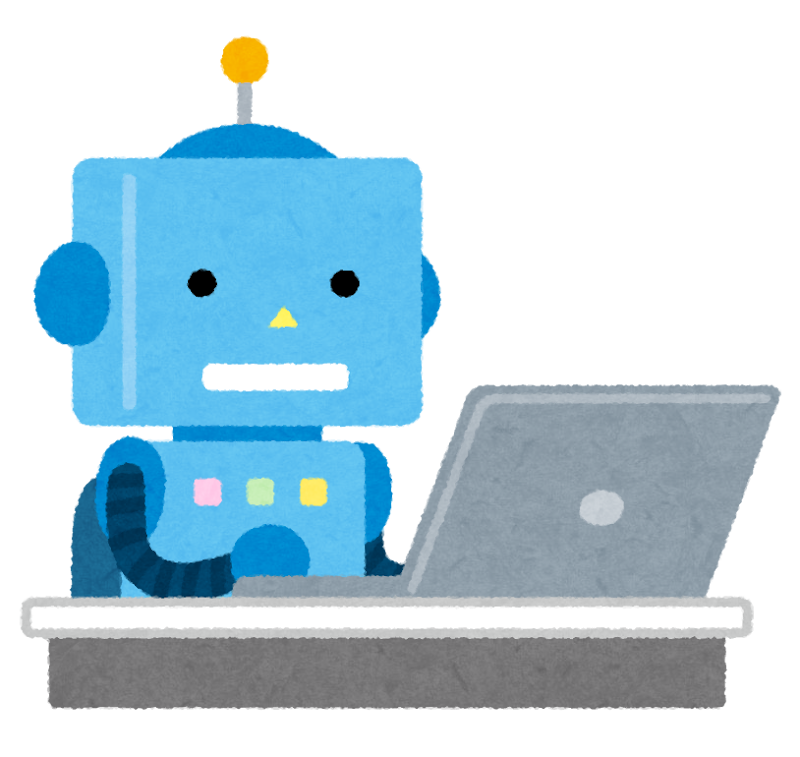
消防設備士は試験範囲が広くて、教科書も分厚いので、勉強が大変です。
とりあえず覚えておけば効率的に勉強できますよ~
消防用設備で工事や整備に資格不要のもの
消防設備士の試験なのに、消防設備士でなくても工事や整備のできるものが問われることがある。
消防用設備等は
- 消防の用に供する設備
- 消防用水
- 消火活動上必要な施設
に分類されます。
消防設備士じゃないと工事、整備できないのはどれでしょうか?
正解は、1の「消防の用に供する設備」です。名前に「消防+設備」が使われているので分かりやすいですね。また、略して、「消防用設備」なので、1~3をまとめて「消防用設備等」と呼びます。
さて、2と3は資格不要で、1に分類されるものは、大半が工事や整備に消防設備士の資格が必要となりますが、1に分類されても、工事や整備に消防設備士の資格が不要なものもあります。それが下記です。
| 消防の用に供する設備 | 消火設備 | 動力消防ポンプ設備 |
| 簡易消火用具 | ||
| 警報設備 | 非常警報器具 非常警報設備 | |
| 避難設備 | すべり台 | |
| 誘導灯、誘導標識 |
これはまとめて語呂合わせで覚えましょう
非常に感動する夕日
⇒非常、感、動、す、夕
⇒非常警報、簡易消火、動力消防ポンプ、すべり台、誘導

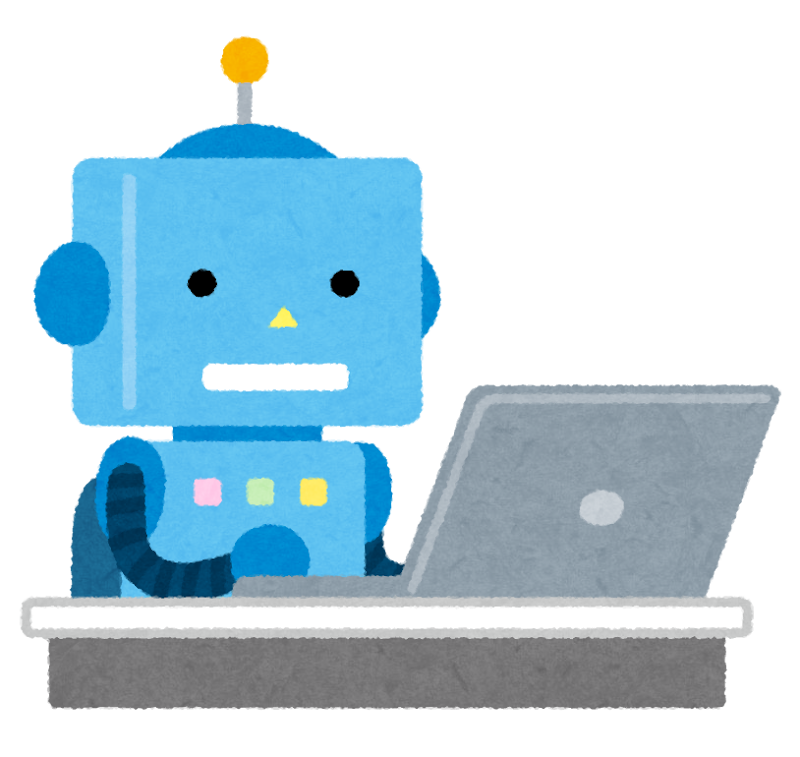
消防設備士の資格なのに、「資格不要」がよく聞かれるので覚えておくと良いですね
消火活動上必要な施設
消防用設備等は
- 消防の用に供する設備
- 消防用水
- 消火活動上必要な施設
に分類されるのですが、2は「水」で分かりやすいですね。
では、1と3は「設備」と「施設」で言葉も似ていてややこしい…そもそも「設備」と「施設」って何が違うの???でもこれってよく問題で出ています
Q:「消火活動上必要な施設」に含まれるものはどれか?
のように。これは覚えるしかないです!
ということで、ここでは「消火活動上必要な施設」を見てみましょう。
| 消防の消火活動上必要な施設 | 無線通信補助設備 |
| 非常コンセント設備 | |
| 排煙設備 | |
| 連結散水設備 | |
| 連結送水管 |
あれ??「消防の消火活動上必要な施設」に、「無線通信補助設備」「非常コンセント設備」「排煙設備」「連結散水設備」など、設備が含まれますね。「設備」なの?「施設」なの?混乱しますね。
語呂合わせで覚えてしまいましょう。
「消防の消火活動上必要な施設」
- む:無線通信補助設備
- こ:非常コンセント設備
- は:排煙設備
- れ:連結散水設備、連結送水管
語呂合わせは「施設の向こうは晴れ」

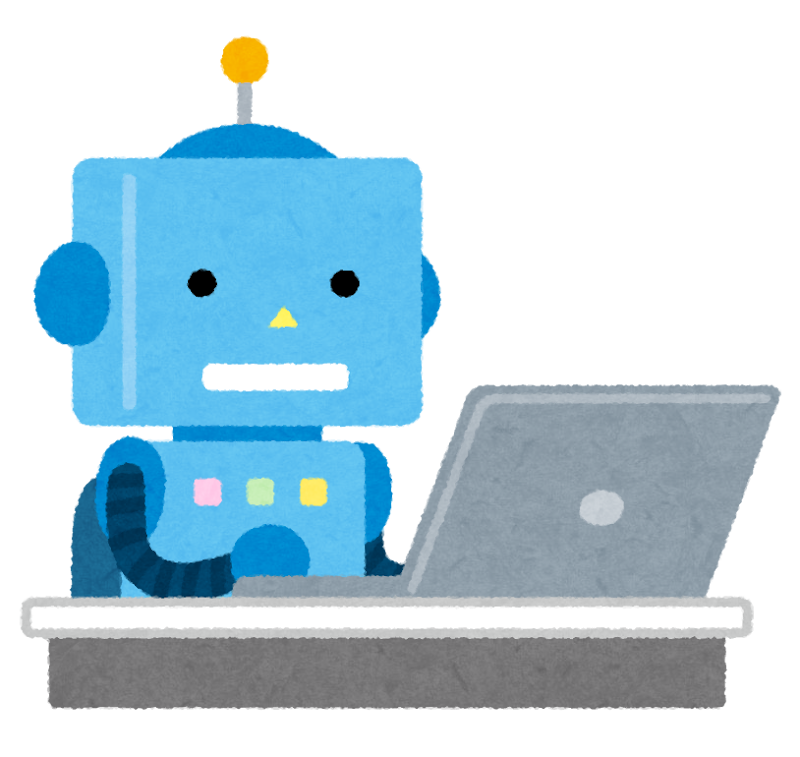
設備だったり施設だったり、言葉がややこしいですが、
ポイントを絞って覚えれば得点ポイントに!
まとめ
いかがだったでしょうか?混乱するような言葉が多いのが消防設備士試験の特徴です。よく出る言葉は語呂合わせでいっきに覚えてしまいましょう!



コメント